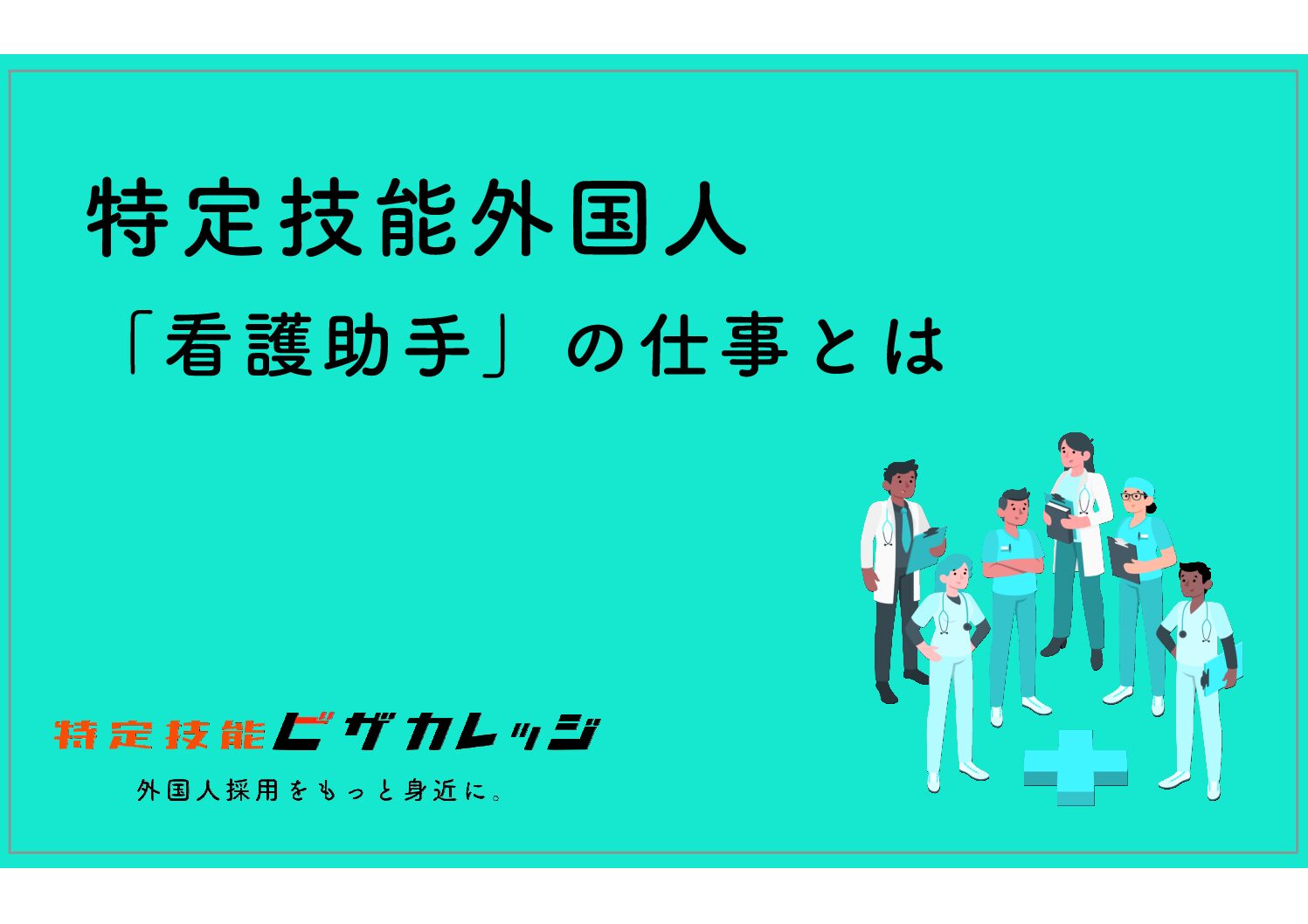日本の医療・介護現場では、慢性的な人手不足が続いており、看護助手の役割がますます重要になっています。こうした状況を受けて、特定技能1号の対象職種に「看護助手」が追加され、外国人材の活用が可能になりました。
そこで本記事では、特定技能「看護助手」の制度概要、取得要件、採用の流れ、メリット・注意点などについて詳しく解説します。
看護助手の人材確保を検討している医療機関や介護施設の担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能「看護助手」とは?

看護助手は看護補助者とも呼ばれ、病院やクリニック、介護施設などにおいて看護師のサポートをおこないます。
以下では、看護助手の役割と介護職との違いについて解説します。
看護助手の役割
看護助手は、医療・介護施設で看護師のサポートを行う職種です。具体的な業務内容は以下のとおりです。・患者の生活支援(食事・入浴・排泄の補助)
・医療機器や病室の清掃・消毒
・備品や医療用品の管理
・看護師や医師の補助(患者移送など)
看護助手は医療行為を行えませんが、病院や介護施設において円滑な業務運営を支える重要な職種です。
介護職との違い
看護助手と混同されがちなのが「介護職」です。両者は業務内容が似ていますが、大きな違いは以下の点にあります。| 項目 | 看護助手 | 介護職 |
| 働く場所 | 病院・診療所・クリニック | 特別養護老人ホーム・デイサービス・訪問介護 |
| 主な業務 | 医療従事者の補助、病室の清掃、物品管理 | 介護サービスの提供(身体介護・生活支援) |
| 医療行為の可否 | 不可 | 状況により一部可能 |
看護助手は、医療現場でのサポート業務に特化した職種である点が特徴です。
特定技能「看護助手」の取得要件
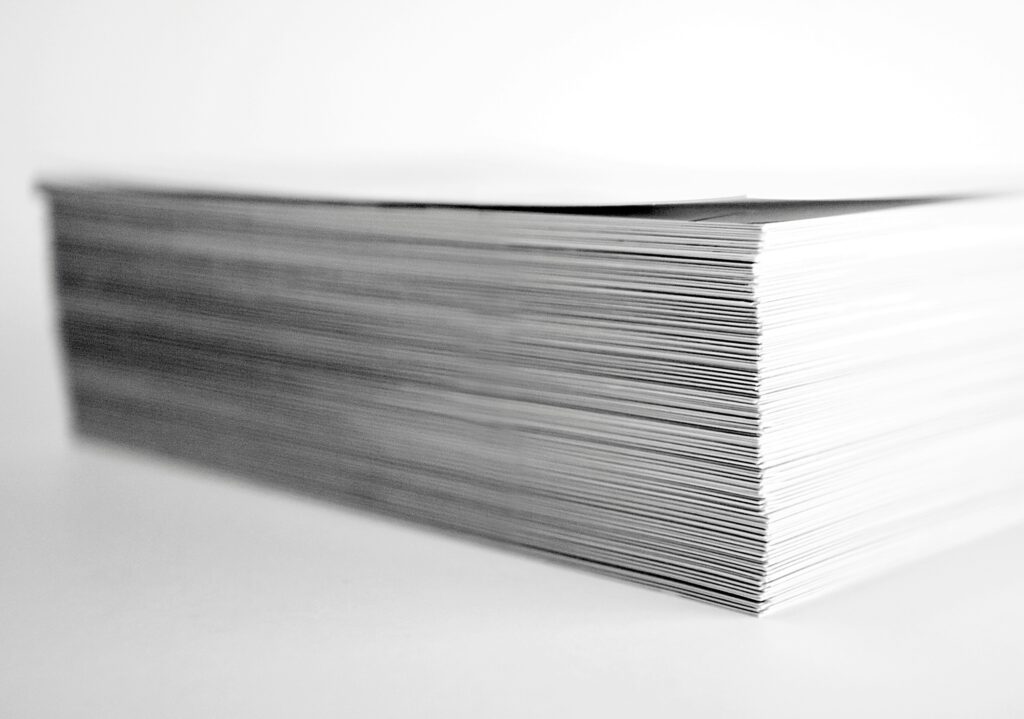
看護助手として働くために必要な特定技能ビザの取得については、以下の3つの試験に合格する必要があります。
これらの試験に合格することで、日本の医療・介護現場で求められる基礎的な技能と日本語能力を有していると認められます。
介護技能評価試験
介護技能評価試験は、看護助手として必要な技能のレベルを測る試験です。この試験に合格すると、利用者の状況に応じた適切な介護を実践できると認定されます。試験概要
• 試験形式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)• 問題数:45問
• 実施国:日本国内およびインドネシア、ベトナムなどの海外主要国 • 試験頻度:原則毎月実施
• 試験結果:試験終了後、コンピューター画面に合否が表示される
この試験は、日本国内外さまざまな国で実施されており、外国人でも受験しやすい仕組みになっています。
日本語能力試験(JLPT)または JFT-Basic
看護助手として働くには、日本語でのコミュニケーション能力が必須です。そのため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。① 日本語能力試験(JLPT)
• 主催:国際交流基金 & 日本国際教育支援協会• 認定レベル:5段階(N1~N5)
• 求められるレベル:N4以上
• 試験頻度:年2回(基本的に7月・12月)
• 試験形式:マークシート方式
JLPTのN4は「基本的な日本語を理解し、日常会話がある程度できるレベル」とされています。
② JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)
• 主催:国際交流基金• 試験目的:特定技能のための日本語基礎力を測る
• 試験頻度:年6回(国内外で実施)
JFT-Basicは、日常生活や職場での基本的なコミュニケーション能力を測る試験です。JLPT N4と同等レベルの能力があると判断されると、特定技能の資格要件を満たします。
介護日本語評価試験
看護助手が医療・介護の現場で働くためには、一般的な日本語能力に加えて、専門的な介護用語やコミュニケーションスキルが求められます。そこで、介護日本語評価試験の合格も必要です。試験概要
• 試験形式:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)• 問題数:15問
• 試験時間:30分
• 試験頻度:原則毎月実施(国内外)
この試験では、利用者や医療スタッフとのコミュニケーションに問題がないレベルの日本語能力が求められます。
特定技能「看護助手」の特徴

以下では、特定技能「看護助手」における基本的な特徴をお伝えします。
在留期間
• 最長5年間の在留が可能• 1年、6カ月、または4カ月ごとに更新
• 5年経過後は帰国が必要(特定技能2号は未設置)
転職の可否
特定技能1号の制度では、同じ分野内での転職が可能です。例えば、A病院からB病院へ移籍することも可能です。家族帯同の可否
特定技能1号では、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることはできません。看護助手の外国人採用方法

最後に、看護助手の外国人を採用する3つの方法を具体的に解説します。
国内の転職者を採用
日本で在留している技能実習生や留学生が、特定技能に切り替えるケースです。日本の生活に慣れているため、定着率が高い傾向にあります。また、同一分野であれば、すでに特定技能ビザで在留している外国人を採用することも可能です。海外から直接採用
海外現地の送り出し機関や人材紹介会社、日本語学校などを活用し、新たに外国人を採用する方法です。言語や文化の壁があり、ビザ申請の手続き等も自社で対応が必要なため、ハードルは高いです。登録支援機関の活用
第三者機関でもある登録支援機関を利用することで、採用から定着支援までスムーズに進めることが可能です。外国人採用のプロであり、まず初めは登録支援機関を利用し、採用人数が増えてきたら自社で内製化する受け入れ施設も多いです。特定技能制度における登録支援機関の役割

特定技能人材を採用する際には、登録支援機関のサポートが不可欠です。
登録支援機関は、特定技能外国人材の採用から定着までを全面的にサポートする第三者機関として、多くの事業者が利用しています。
入国前の事前ガイダンスや入国時の送迎およびサポート、住居確保や生活支援、日本語教育の機会提供など、外国人介護者が安心して働ける環境を整えるための包括的な支援を提供しています。
全てを自社で内製化することも可能ですが、特定技能外国人材を初めて受け入れる場合は非常にハードルが高く、ビザ申請時の必要書類等も膨大なため、基本的には登録支援機関を利用する事業者がほとんどです。
一部業務を登録支援機関に任せることで、事業者は特定技能外国人材の受け入れに集中でき、外国人材を活用した介護業務をスムーズにスタートさせることができます。
外国人看護助手の採用はFuntocoへお任せ

登録支援機関である弊社「Funtoco」は、特に医療・介護業界における特定技能人材の紹介や支援業務、各種相談業務を強みとしております。
弊社では、累計1,000名以上の特定技能外国人を事業者様にご紹介してきました。
日本で初めてミャンマー人の特定技能ビザを介護分野で取得したのも、Funtocoです。

また、圧倒的に高い定着率が強みで、弊社が紹介する特定技能介護人材の定着率は90%以上となっています。
ビザの取得には一定の期間が必要なため、特定技能ビザでの看護助手の採用を検討中の事業者様は、早めに動き出しておくことをおすすめします。
 株式会社
株式会社